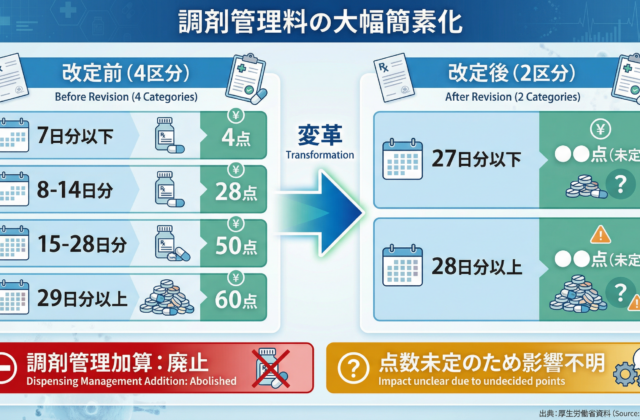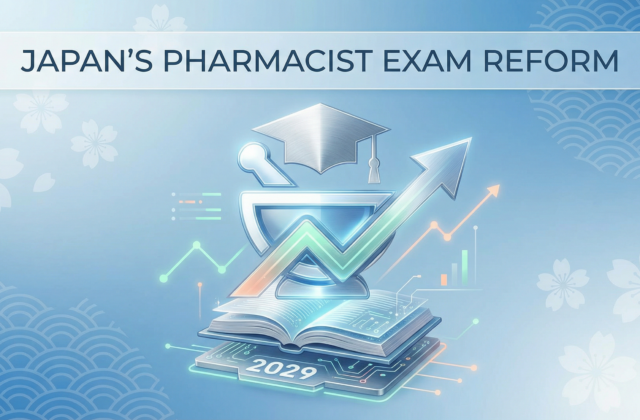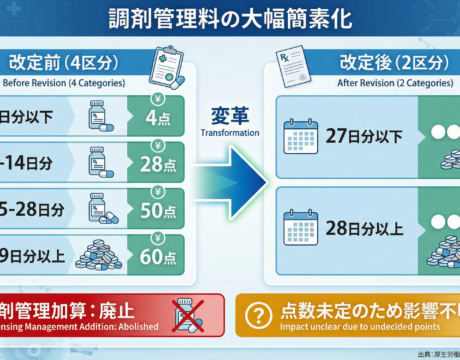更新日:2025/10/3
訪問介護・通所介護の軽度者除外? 第125回社会保障審議会介護保険部会レポート

訪問介護・通所介護の軽度者に対する見直しについて
こんにちは<m(__)m>
今回は以前から議論されている内容で、皆さんも非常に気になっているであろう訪問介護や通所介護を利用されている軽度者(要介護1、2)に対する給付の見直しについて、最新の動向をお伝えいたします。
2025年9月30日に開催された「第125回社会保障審議会介護保険部会」では、介護保険制度の持続可能性をめぐる重要なテーマが議論されました。特に注目を集めたのは、要介護1・2の軽度者に対する訪問介護・通所介護を保険給付の対象から外すかどうかという問題です。
このテーマはここ数年繰り返し議論されており、現場の介護従事者・施設経営者・利用者家族にとって大きな関心事となっています。今回は、その内容と今後の見通し、そして介護現場に及ぶ可能性のある影響について整理します。
◇なぜ「軽度者除外」が議論されるのか
日本の介護保険制度は2000年にスタートして以来、高齢化の進行とともに利用者数・給付費が急増しています。特に要介護1・2の比較的軽度な高齢者が訪問介護やデイサービスを利用するケースは年々増加。
その結果、介護保険財政への負担が大きくなり、制度の持続可能性が懸念されています。
国はこれまでも「自立支援」「地域包括ケアシステム」を強調し、軽度者についてはできるだけ住民主体のサービスや総合事業(自治体による介護予防事業)に移行させたい考えを示してきました。
◇2025年9月30日の議論のポイント
今回の部会では、以下のような論点が取り上げられました。
- 訪問介護(生活援助)・通所介護の給付見直し
- 要介護1・2の生活援助(掃除・買い物など)や通所介護の一部を保険給付から外す案が提示されました。
- 代替として「総合事業」や住民ボランティアの活用が想定されています。
- 現場からの懸念の声
- 「軽度」とはいえ独居高齢者や認知症の初期段階の方にとって、生活援助や通所介護は生活の質や安全に直結する。
- ボランティアや地域サービスだけでは十分に支えきれない可能性がある。
- 経営への影響
- 通所介護事業所では、利用者の約3~4割が要介護1・2であるケースも多く、除外されれば経営に大きな打撃となる。
- 特に小規模デイサービスは存続が危ぶまれる。
- 制度の方向性
- 「保険給付は重度者中心へ、軽度者は地域支援へ」という流れを加速させるべきとの意見が一部委員から示された。
- 一方で「地域の受け皿が不十分なまま移行すれば、介護難民が増える」との強い反対意見もあり、結論は持ち越しとなりました。
◇現場への影響をどう考えるか
- 介護従事者への影響
- 利用者数が減少すれば、シフト削減や人員調整が必要になる可能性があります。
- 一方で、軽度者支援が総合事業に移行すれば、介護職が地域支援や予防事業に関わる新たな役割が期待されるかもしれません。
- 施設・事業者への影響
- デイサービスや訪問介護事業所にとっては経営の根幹に関わる大問題です。
- 特に要介護1・2の利用割合が高い事業所では、事業転換やサービス多角化の必要性が出てくるでしょう。
- 利用者・家族への影響
- 「掃除や買い物だけなら家族で」と言われても、家族の負担は増加。
- サービス利用が減ることで高齢者の閉じこもりや認知症進行が加速するリスクもあります。
今後の見通し
今回の部会では結論が出なかったものの、国は財政面から「軽度者の保険給付縮小」の方向性を強めています。2026年度の介護保険制度改正に向けて、来年以降さらに具体的な制度設計が議論される見通しです。
現場にとって重要なのは、国の動きを注視しつつ、以下のような対応を準備することです。
- 要介護1・2の利用者割合を把握し、経営リスクを試算する
- 総合事業への参入や地域包括支援センターとの連携を検討する
- 利用者・家族に対して情報提供を行い、不安を軽減する
まとめ
「軽度者の訪問介護・通所介護除外」は、単なる制度改正ではなく、介護現場の在り方そのものを変える可能性を持つ議論です。
介護施設従事者や経営者の皆さんにとって、今後数年は制度の変化を見据えながら柔軟な対応を進めることが求められます。
厚労省は引き続き関係者と議論を深める構えで最終的な判断は、今秋に誕生する新たな政権の枠組みが年内に下すことになる。
大変重要な事ですので、今後も注目していきたいと思います。